

「ヨガを深く学んでみたい」「資格を取って仕事にできたらいいな」そんな思いが芽生えたとき、まず耳にするのが「RYT200」という言葉かもしれません。
でも実際に調べ始めると、「30万円って高い?」「オンラインでも大丈夫?」「取っても仕事になるの?」と、不安や疑問がどんどん湧いてきますよね。
表には出にくい本音の部分や、経験者だから分かる選び方のコツ。
この記事では、RYT200について表面的な情報だけでなく、あなたが本当に知りたいと思っている部分まで、丁寧にお伝えしていきます。
CONTENTS
1. RYT200って何だろう?—— 資格の価値と誤解されやすいこと

ヨガインストラクター資格を調べ始めると、必ずといっていいほど出てくる「RYT200」という言葉。
これは、Registered Yoga Teacher(登録ヨガティーチャー)の略で、全米ヨガアライアンスという国際的な非営利団体が認定する資格です。
数字の「200」は、最低200時間のトレーニングを修了したことを意味しています。
世界的に認知されている基準であるため、この資格を持っていることで「一定の学びを積んだ人」として信頼されやすくなります。
ヨガスタジオの求人でも「RYT200保持者」という条件をよく見かけるでしょう。
ただし、ここで誤解されやすいのが、「RYT200を取れば即戦力のインストラクターになれる」という思い込みです。
実際には、資格取得直後はまだスタート地点。
多くの人が「こんなに分からないことがあるなんて」と驚くほど、実践には経験が必要です。
それでも、体系的な知識と基礎があることで、その後の学びがスムーズになりますし、何より「自分はちゃんと学んだ」という自信が、人前に立つときの支えになります。
また、RYT200以外にもヨガの資格は存在しますが、全米ヨガアライアンスの認定は国際的な通用性があるため、将来的に海外で教えたい人や、さまざまな場所で活動したい人にとっては有力な選択肢となります。
2. 費用はどれくらい?—— 相場と「高い・安い」の見極め方

RYT200の取得にかかる費用は、30万円〜50万円程度が一般的な相場です。
地域や受講スタイル、スクールの規模によって幅があります。
20万円〜30万円前: オンライン講座や動画視聴型のコースに多い価格帯です。
費用を抑えられる反面、講師からの直接的なフィードバックが限られ、実技の細かい指導を受けにくい傾向があります。
また、録画視聴が中心になるため、疑問が湧いてもその場で解消できず、学びが一方通行になりがちです。
教材や修了証発行費が別途かかる場合もあるため、最終的な総額を確認しておきましょう。
すでにヨガ経験が豊富で、自己学習ができる人には向いていますが、初めて本格的に学ぶ人にとっては物足りなさを感じることもあります。
30万円中〜40万円中: 対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型や、通学型のスクールに多く、最もバランスの取れた価格帯といえます。
講師との距離が近く、質問や実技指導の機会がしっかり確保されていることが多いです。
少人数制のクラスであれば、一人ひとりの体の使い方を見てもらえたり、疑問に丁寧に答えてもらえたりと、学びの質が高まります。
カリキュラムの内容や講師の専門性、卒業後のサポート体制なども比較的充実している傾向があり、「ちゃんと学べた」という実感を得やすい環境です。
初めてヨガを深く学ぶ人や、将来的にインストラクターとして活動したい人には、この価格帯のスクールをじっくり比較検討することをおすすめします。
40万円中〜50万円中: 著名講師による指導や、超少人数制、長期にわたる手厚いサポートが付いているスクールに多い価格帯です。
卒業後のフォローアップや就職支援、コミュニティへのアクセスなども含まれていることがあります。
ただし、この価格帯では「何にお金を払っているのか」を冷静に見極めることが大切です。
ブランド力や講師の知名度だけで選ぶのではなく、自分が本当に必要とするサポートや環境が含まれているか、費用に見合った価値があるかをしっかり確認しましょう。
ここで大切なのは、「安ければお得」でも「高ければ質が良い」でもないということです。
30万円台後半から40万円前後のスクールであれば、講師の質、カリキュラムの充実度、サポート体制のバランスが取れていることが多く、納得のいく学びが得られる可能性が高いでしょう。
見極めるポイントは以下の通りです。
- 講師との距離感:質問しやすい環境か、一人ひとりにフィードバックがあるか
- 実技練習の時間:動画を見るだけでなく、実際に体を動かして学ぶ時間が十分にあるか
- ライブ授業の有無:リアルタイムで講師とやり取りできる機会があるか
- クラスの人数:講師1 人につき〜15人程度の少人数制かどうか
- 卒業後のサポート:復習会、コミュニティ、仕事紹介などがあるか
- 教材の質:テキストや資料が分かりやすく、後で見返せる内容か
- 追加費用の有無:表示価格に何が含まれていて、何が別途必要なのか
また、分割払いに対応しているスクールも増えています。
無理のない範囲で学べる環境を選ぶことも、長く続けるためには大切な視点です。
焦らず、複数のスクールを比較しながら、自分にとって納得のいく選択を見つけてみてください。
3. 学ぶ期間と受講スタイル—— それぞれのメリット・デメリット

RYT200は最低200時間の学習時間が必要ですが、その時間をどう配分するかで、学びの深さや定着度が変わってきます。
ここでは、主な3つのスタイルについて、メリットとデメリットを整理してみます。
短期集中型(10日〜1ヶ月程度)
海外や国内のリトリート形式で行われることが多く、仕事を休んで一気に学ぶスタイルです。
メリット:
集中して没頭できるため、短期間で資格が取れる。
ヨガ漬けの日々を過ごすことで、心身の変化を実感しやすい。
デメリット:
情報量が多く、消化不良になりやすい。帰宅後に復習をすると寝る時間が減りがち。
日常生活との接続が難しく、心身に少なからずストレスになっている。
通学型(3ヶ月〜半年)
週末や平日夜に通いながら、じっくり学ぶスタイル。仕事や家庭と両立しやすいのが特徴です。
メリット:
学んだことを日常で試しながら進められるため、定着しやすい。
クラスメイトとの交流も深まり、仲間ができる。疑問や気づきを次の授業で確認できる。
デメリット:
長期間通う必要があるため、スケジュール調整が必要。
通学の負担や、モチベーション維持が課題になることも。
オンライン型(自分のペースで)
自宅にいながら学べるスタイル。録画視聴とライブ授業を組み合わせるスクールが多いです。
メリット:
場所を問わず学べるため、地方在住者や育児中の人にも最適。
移動時間がなく、費用も抑えられる傾向がある。
デメリット:
実技の細かい指導が受けにくい。画面越しでは体の使い方の微妙なズレに気づきにくく、自己流になるリスクも。
孤独を感じやすく、モチベーション維持が難しい人もいます。
どう選ぶ?
自分の生活リズム、学び方の好み、予算を総合的に考えて選ぶことが大切です。
たとえば、「まずはオンラインで基礎を学び、卒業後に対面のワークショップに参加する」といった組み合わせ方もあります。
学びは一度きりではなく、続いていくもの。焦らず、自分に合ったペースを見つけてみてください。
4. 講師の選び方—— 見るべきは経歴だけじゃない

ヨガ資格の取得において、「誰から学ぶか」は、知識や技術以上に大きな影響を与えます。
講師の経歴や肩書きはもちろん参考になりますが、それだけで判断するのは危険です。
専門性と教え方のバランス
解剖学に詳しい講師、哲学を深く学んでいる講師、マインドフルネスに特化している講師など、それぞれに強みがあります。
ただし、専門知識が豊富でも、それを初心者に分かりやすく伝えられるかは別の話です。
「すごい人」ではなく、「自分が理解できる言葉で伝えてくれる人」を選ぶことが大切です。
押しつけない姿勢があるか
ヨガには流派や考え方がたくさんあります。
「これが正しい」と一方的に教える講師ではなく、「あなたにとってどうか」を一緒に考えてくれる講師のもとで学ぶと、卒業後も自分で考える力が育ちます。
講師自身が学び続けているか
ヨガは変化し続けるものです。
講師自身が学び続けているか、最新の知見を取り入れているか、自分の体と向き合い続けているかは、プロフィールやSNS、ブログから感じ取れることもあります。
実際に会って確かめる
可能であれば、体験レッスンや説明会に参加してみましょう。
講師の話し方、表情、受講生への接し方を見ることで、「この人から学びたい」と思えるかどうかが分かります。
直感も大切にしてください。
あなたの心が「ここにいたい」と感じる場所が、あなたにとっての正解です。
5. スクール選びで見落としがちな重要ポイント
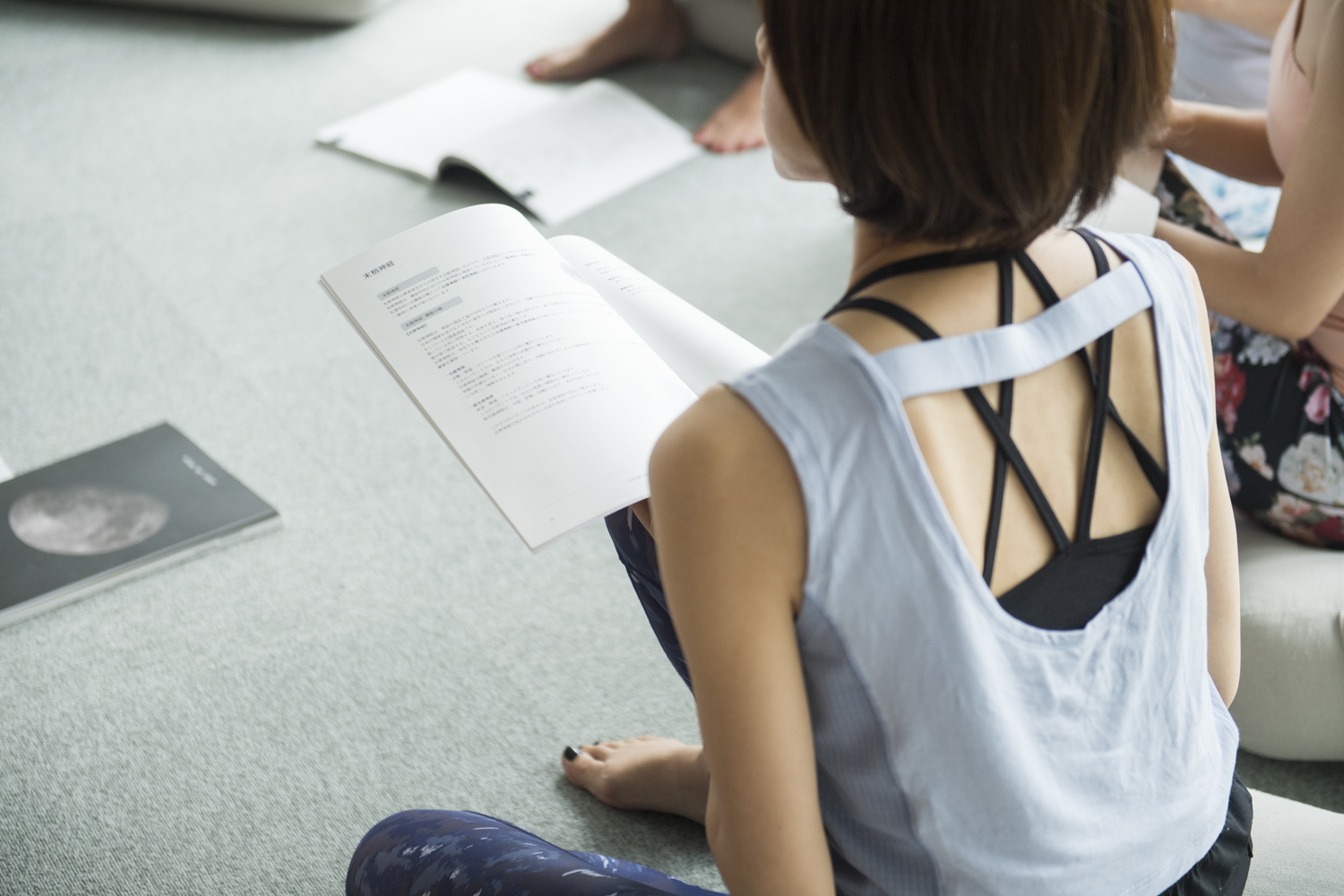
RYT200を取得できるスクールは数多くありますが、表面的な情報だけでは分からない部分があります。
ここでは、見落としがちだけど重要なポイントをお伝えします。
カリキュラムの中身を具体的に確認
「哲学、解剖学、アーサナ、呼吸法を学べます」と書いてあっても、それぞれに何時間割かれているかで深さが変わります。
たとえば、解剖学が5時間しかないのか、30時間あるのかでは大違いです。
可能であれば、時間配分の内訳を確認しましょう。
クラスの人数
「少人数制」と書いてあっても、10人なのか30人なのかで環境は大きく変わります。
理想は10人前後。講師の目が一人ひとりに届き、質問もしやすい人数です。
卒業生の声をチェック
公式サイトに載っている感想だけでなく、SNSやブログで実際の卒業生が何を発信しているかを見てみましょう。
リアルな体験談が見えてきます。
途中で辞めた場合の対応
人生には予期せぬことが起こります。
体調不良や家庭の事情で通えなくなったとき、休学制度や返金制度があるかも確認しておくと安心です。
卒業後のつながり
資格を取った後、孤独を感じる人は少なくありません。
卒業生コミュニティや練習会、勉強会があるスクールは、学び続ける環境として心強い存在になります。
スクールの理念に共感できるか
「ビジネスとしてのヨガ」を重視するスクールもあれば、「心の在り方」を大切にするスクールもあります。
どちらが良い悪いではなく、あなたの価値観と合うかどうかが大切です。
サイトの文章や写真から、スクールの空気感を感じ取ってみてください。
6. 資格を取った後のリアル—— 知っておきたいこと

RYT200を取得した後、多くの人が直面するのが「で、どうすればいいの?」という現実です。
ここでは、資格取得後のリアルについてお伝えします。
すぐに仕事になるとは限らない
資格を取ったからといって、すぐにヨガスタジオから声がかかるわけではありません。
オーディションを受けたり、まずは無償や低額でクラスを持って経験を積んだり、SNSで発信を続けたりと、地道な努力が必要です。
それでも、学んだことは確実にあなたの中に残ります。
自分のヨガが深まる
仕事にならなくても、自分自身のヨガが変わります。
体の使い方が丁寧になり、呼吸が深くなり、日常の中で心を整える方法が身につきます。
それだけでも、学んだ価値は十分にあります。
学び続けることが前提
RYT200はゴールではなく、スタートです。
多くの人が、卒業後にワークショップに参加したり、集客などに関する別の講座を受けたり、RYT500(上位資格)を目指したりします。
学び続ける姿勢が、インストラクターとしての信頼につながります。
自分らしい形を見つける
ヨガスタジオで教えるだけが選択肢ではありません。
企業や学校でのヨガ講師、オンラインレッスン、パーソナル指導、ヨガリトリートの企画など、働き方は多様です。
あなたらしい形を、焦らず探してみてください。
7. よくある疑問に答えます
体が硬くても大丈夫?
大丈夫です。
むしろ、体が硬い人の方が、無理なく体を動かす方法を体感的に学べます。
柔軟性よりも、体と向き合う姿勢が大切です。
年齢制限はある?
ほとんどのスクールに年齢制限はありません。
20代から70代頃まで、幅広い年齢層の人が学んでいます。
ヨガ経験が浅くても大丈夫?
多くのスクールは、1年程度のヨガ経験を推奨していますが、未経験者でも受け入れているところもあります。
不安な場合は、事前に相談してみましょう。
全米ヨガアライアンスへの登録は必須?
RYT200を取得しても、アライアンスへの登録は任意です。
登録には年会費がかかりますが、会員が見れる学びコンテンツも充実しているので、登録する価値はあります。
8. まとめ—— 資格は、自分と向き合う時間のはじまり

ヨガ資格RYT200は、世界的に認められた基準であり、ヨガを深く学ぶための入り口です。
費用や期間、講師やスクールの選び方は、あなたの暮らしや価値観によって変わります。
大切なのは、表面的な情報だけでなく、自分にとって本当に必要な学びは何かを見極めること。
資格を取ることがゴールではなく、そこからがスタートです。
学びの過程で出会う気づき、体と心の変化、人とのつながり。
それらすべてが、あなたのこれからを支える土台になっていきます。
焦らず、比べず、自分のペースで。
そして、「これでいいんだ」と思える選択を、信じて進んでみてください。
あなたがヨガと出会い、自分らしく学び続けられる場所が見つかりますように。